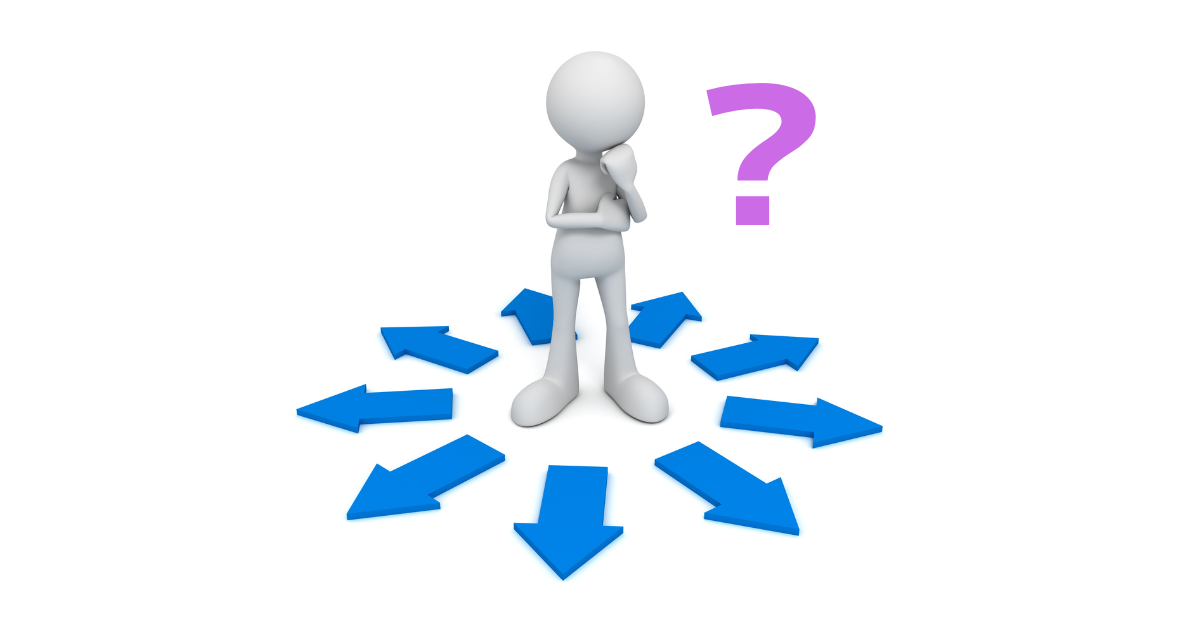税理士試験受験生の時、試験合格に少しでもプラスになると思うことは何でもやっていました。
しかし、最後の相続税を受験してから5年経った今振り返ってみると、それらの行動に対して「ん?」と思う点がいくつかあります。
今回はそんな「ん?」と思える税理士試験受験生時代の行動について振り返ってみます。
5科目パック70万円一括払い
私は税理士試験の予備校はTACを選びましたが、TACに入学する際、スタッフの方から「以下のプランの内どれを選びますか?」と案内されました。
- 1科目ずつ払う(約20万円)
- 初年度受験する簿記論と財務諸表論の2科目パックを選ぶ(約35万円)
- 5科目パックを選ぶ(約70万円)
私は何の躊躇いもなく5科目パック70万円を選択しました。
独学日商簿記1級のブログにも書いていますが、この時の私は人生を懸けて税理士試験に挑戦することを決めたので、70万円を一括で払うことに迷いなど全くありませんでした。
むしろこれをやることで税理士試験から撤退できない状況を強制的に作ったと言えます。
税理士になることができなければ人生が終わるという覚悟を持っていたので、5科目パック70万円一括払いで逃げ道を無くすことは逆に好都合とさえ思っていました。
しかし今思い返すとこの判断は結構狂っています。
なぜなら当時の私の月収は18万円!!(笑)
しかも社保なし!!(笑)
30歳で月収18万円(+社保なし)という評価が示すように、当時の私は何の価値も能力も実績もない人間でした。
そんな人間が受かるかどうかも分からない税理士試験の為に約4ヶ月分の給与をポンと支払っていたのです。
非常に恐ろしい選択をしていますね。
ただしこの狂った選択が最高の結果に繋がる大きな一歩だったのは間違いありません。
「貯金も無くなったし、もう後には引けない」
「税理士試験に合格する以外に道はない」
70万円一括払いで頑張って貯めていた貯金も無くなり、私に残ったのは社保なし月18万円の評価と日商簿記2級+運転免許の資格だけでした。
30歳でこれはキツすぎる(笑)。
この時点で半分人生終わっているようなものだったので、税理士試験に合格しなければ本当に人生が終わるという状況を作り上げたのです。
このように金銭的にも精神的にも崖っぷちに立たせたおかげもあり、税理士試験に挑戦した5年間は常に最高のテンション感を維持しながら勉強することができました。
結果として5科目パック70万円一括払いは、最高の選択だったと言えます。
しかし他の人には一括払いはおススメしません。
まずは安全策の簿財2科目パックを選択するのが無難だと思います(笑)。
自分が担当のお客様に毎回受験する科目とその結果を報告する
税理士事務所で働いていた時、私は年30~40件程のお客様の担当でした。
その中で頻繁に会ったり連絡を取り合うお客様には毎年受験する科目とその結果を報告するようにしていました。
「不合格が続けばお客様から無能だと思われ、信頼を失ってしまう」というプレッシャーを自分にかける為です。
当然のことですが、税理士試験経験者でない限り、税理士試験の本当の難しさは理解してもらえません。
以下、5科目合格後に実際にあった会話です。
鈴木さん、税理士試験に合格するのに何年くらいかかりました?

フルタイムで働きながら5年で合格しました!(ドヤー)
え!?そんなにかかったんですか!?大変でしたねー



は、はい大変でした…(ショボーン)
これが現実です(笑)。
普通の人は税理士試験=難しい試験という認識を持っていても、フルタイムで働きながら5年で5科目がすごいとは思ってくれません。
むしろ「5年もかかったの?お前ヤバくね?」という印象を持たれることもあります(笑)。
だからこそ、何年も合格できないでいると、
「鈴木、また落ちたのかよ」
「いつになったら受かるんだよ」
「鈴木って無能なんじゃないの?」
「こいつが担当で本当に大丈夫なの?」
「所長先生に言って担当を変えてもらおう」
というお客様の声が大きくなり、その結果所長の評価も下がり、給料が再び月18万円に戻るという最悪のストーリーを常に頭の中で作っていました(笑)。
私が担当していたお客様は基本的に皆さん器が大きく優しかったので、上記のようなことが起こることはありえないのですが、「毎年合格すると思ってくれているお客様の期待を裏切ってはいけない!」というプレッシャーは常に持っていました。
それぐらい自分を追い込まないと合格できない試験だと思っていました。
「お客様の信頼を失いたくない」「無能だと思われたくない」というプレッシャーを勝手に作り上げ、それを力に変えていました。
実際最初の3年で3科目取ったぐらいから、「鈴木は毎年受かる」的な空気が出てきて、
「鈴木さん、今年も受かるんでしょ?」
「あと2回で終わりだね」
と言われることもあり、最後の2年のプレッシャーは半端なかったですが、私はこれらのプレッシャーを力に変えて、勉強する糧にしていました。
結果的に5年間毎年合格をお客様に報告できたので、良かったです。
税理士試験の合格発表は12月下旬だったので、年末の挨拶の際に結果も報告していました。
最初の2年は不合格科目もあったので、1個は合格しているのに何とも言えない微妙な空気が流れましたが、最後の3年は合格科目しかなかったので、微妙な空気は一切生まれず、非常に良い気分で年を越すことができました(笑)。
私の合格を自分のことのように喜んでくれるお客様もおり、今でもその時の光景は忘れられません。
しかし、これも今振り返ると全くやる必要のない行動ですね。
税理士試験は100人中10~15人程しか受からないものを5個突破しないといけないので、5個揃えるまでには不合格になる確率の方が圧倒的に高いです。
そんなヤバイ試験の受験科目とその結果を多くのお客様に毎回報告するなんて、自分にプレッシャーをかける以外何のメリットもありません。
今ならこんなリスキーなこと、「何の疑問も持たずにできるか?」と言われると悩んでしまいます。
お客様の信頼を失ったり無能だと思われるリスクが高い行動をとってまでプレッシャーをかけて、それさえも力に変えようとしていた当時の自分の思想が恐ろしいです(笑)。
激熱の風呂で命懸けの理論暗記
これは最後の相続税の時に思いついた勉強方法です。
自宅の風呂を45℃に設定して、激熱湯船に浸かり汗だくになりながら理論マスターを覚える。
一つの理論を覚えきるまでは絶対に湯舟から出てはいけないルールを自分に課しました。
理論を覚えずに湯船から出たらアウト!(根性なし!)
理論を覚える前に力尽きてブラックアウトしてもアウト!(覚えるのが遅い!)
セーフになるには力尽きる前に覚えるしかないという、シンプルな命懸けの戦い。
この勉強法を思いついた時、「俺は天才じゃないか!」と思いましたが、単に狂っているだけです(笑)。
相続税を受験した年はコロナ元年で、TACの理論自習室も例年より使える機会が少なかったので、自宅の風呂で覚えるというのは良い視点かなと思いますが、何故に風呂の温度を45℃縛りにしたのか意味が分かりません(笑)。
普通に快適な温度にしてリラックスして覚えればいいのに…。
なお、相続税の理論マスターはこの命懸け風呂理論のせいで、他の科目の理論マスターより明らかに損傷が激しく色も薄くなっています(笑)。
結論:受験生時代は結構狂っていた
こんな感じで、当時は何の違和感も感じずに当たり前にやっていた行動も、5年経った今では「ん?」と思えてしまいます。
結構狂っている行動もありますが、それぐらいじゃないとフルタイムで働きながら順調に合格することはできなかったんだろうなと思います。
そもそも法人税や相続税の200ページを超える分厚い理論マスターを全部覚えた時点で相当狂っているので、まあこれくらいは別に普通なんじゃないかと…(笑)。
これ以外にも更に狂っている行動もしていたのですが、さすがにブログには書けないのでここら辺で終わりにしておきます(笑)。
<メニュー>